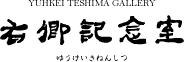
手島右卿記念室
手島右卿記念室
昭和の三筆・現代書の先駆者
「昭和の三筆」と称えられる現代書の先駆者・手島右卿。現代書道を語る上では欠かすことのできない超俗孤高の巨匠です。
手島右卿は1901年11月3日、高知県安芸市に誕生しました。
川谷尚亭、比田井天来に師事し、中国や日本の古典を徹底的に追及すべく厳しい鍛錬を積み重ね、あらゆる臨学・書法を会得しましたが、右卿は満足しませんでした。
東洋の哲理に則りながら現代人の美意識をも触発する書を―。
長きに亘る試行錯誤の末、ついに「象書」(文字の内容に相応しい形の書を創作すること)という造形性豊かな新しい様式美を確立したのです。
そして、象書作品の代表作「崩壊」(1957年)「抱牛」(1955年)が世界で高い評価を得ました。
その後も右卿は独創的で耽美的な代表作を制作し続け、国内外の人々に感動を与え続けたのです。
1987年3月、書に全てを捧げた右卿は、極めて霊性の高い書「神」(1974年)「鶴舞」(1985年)「以虚入盈」(1987年)を創作して86年の生涯を閉じました。
右卿が残した数々の名作は今、深い緑に囲まれた飛騨高山にある光ミュージアムの一室に飾られています。
右卿記念室では手島右卿の書業を顕彰するべく、若き頃から晩年に至るまでの主な代表作、資料、愛用の品々を展示しております。
展示作品
書
| 作品 | 西暦 | 和暦 | 年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 背山臨濤 | 1949 | 昭和24年 | 48歳 |
| 2 | 山行 | 1948 | 昭和23年 | 47歳 |
| 3 | 緑化荒山 | 1961 | 昭和36年 | 60歳 |
| 4 | 弾琴 | 1955 | 昭和30年 | 54歳 |
| 5 | 雷音 | 1987 | 昭和62年 | 86歳 |
| 6 | 蓮 | 1959 | 昭和34年 | 58歳 |
| 7 | 天上十分月… | 1971 | 昭和46年頃 | 70歳頃 |
| 8 | 光風万里 | 1984 | 昭和59年 | 83歳 |
| 9 | 鳩啼山関雨 鴬出宮墻花 | 1967 | 昭和42年 | 66歳 |
| 10 | 詩懐 | 1974 | 昭和49年 | 73歳 |
| 11 | 一陣風聲似鼓琴 | 1970 | 昭和45年頃 | 69歳頃 |
| 12 | 秋風引 | 1969 | 昭和44年頃 | 68歳頃 |
| 13 | 夜半和風剉窓紙… | 1952 | 昭和27年頃 | 51歳頃 |
| 14 | 崩壊 | 1957 | 昭和32年 | 56歳 |
| 15 | 幻 | 1982 | 昭和57年頃 | 81歳頃 |
| 16 | 含 | 1983 | 昭和58年 | 82歳 |
| 17 | 鈍 | 1968 | 昭和43年 | 67歳 |
| 18 | 潭 | 1983 | 昭和58年 | 82歳 |
| 19 | 岳雲 | 1960 | 昭和35年 | 59歳 |
| 20 | 看梅詩 | 1971 | 昭和46年 | 70歳 |
| 21 | 鏤月 | 1964 | 昭和39年 | 63歳 |
| 22 | 渦 | 1987 | 昭和62年 | 86歳 |
| 23 | 抱牛(複製・陶板) | 1955 | 昭和30年 | 54歳 |
| 24 | 土佐之書 | 1975 | 昭和50年 | 74歳 |
| 25 | トマト | 年代不詳 | ||
| 26 | 為 | 年代不詳 | ||
| 27 | 樹 | 年代不詳 | ||
| 28 | 木簡臨書 | 1971 | 昭和46年頃 | 70歳頃 |
| 29 | 鳥度屏風裏 人行明鏡中 | 1976 | 昭和51年 | 75歳 |
| 30 | 沙 | 1965 | 昭和40年 | 64歳 |
その他
草稿、未表装作品、文房四宝(筆・硯・紙・墨)、落款印
手島右卿記念室ご利用案内
右卿記念室の観覧可能時間は10時~16時です。
展示替えやその他都合により、ご鑑賞いただけない場合がございます。
- チケット
- 鑑賞ご希望の場合は当日チケット売り場でお申し出下さい。
- 入室料金
- 100円(光ミュージアム入館料金は別途必要です)
※料金は消費税込み。小学生未満は無料。





※光ミュージアムの入館料以外に、別途100円の入室料金が必要です。詳しくは下記の手島右卿記念室ご利用案内をご覧下さい。